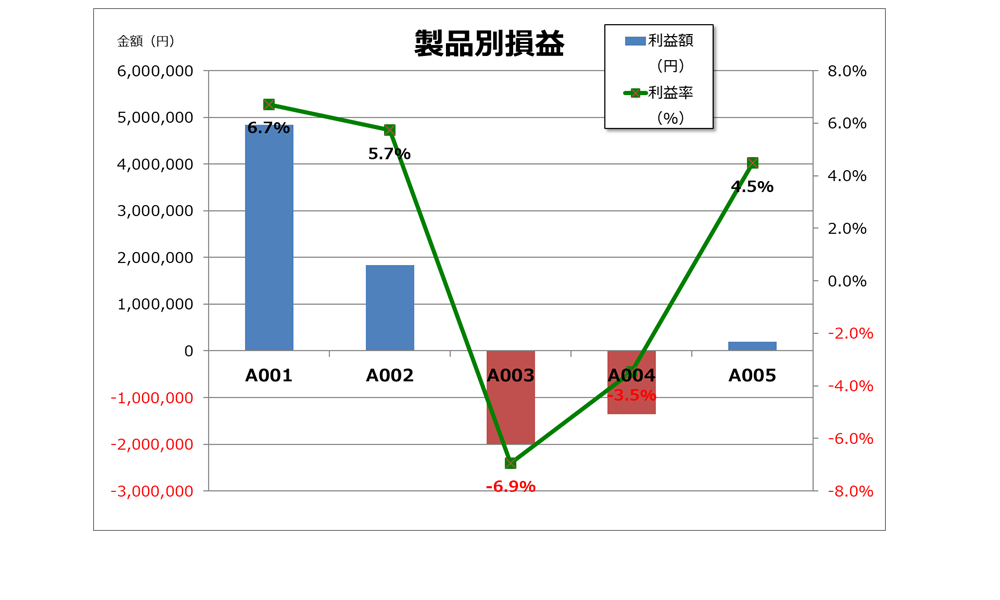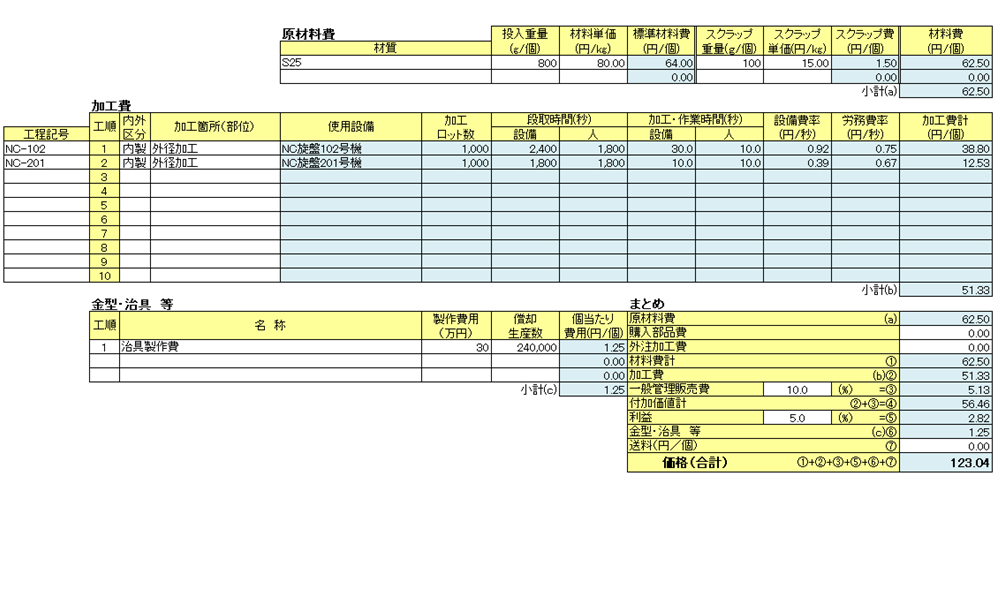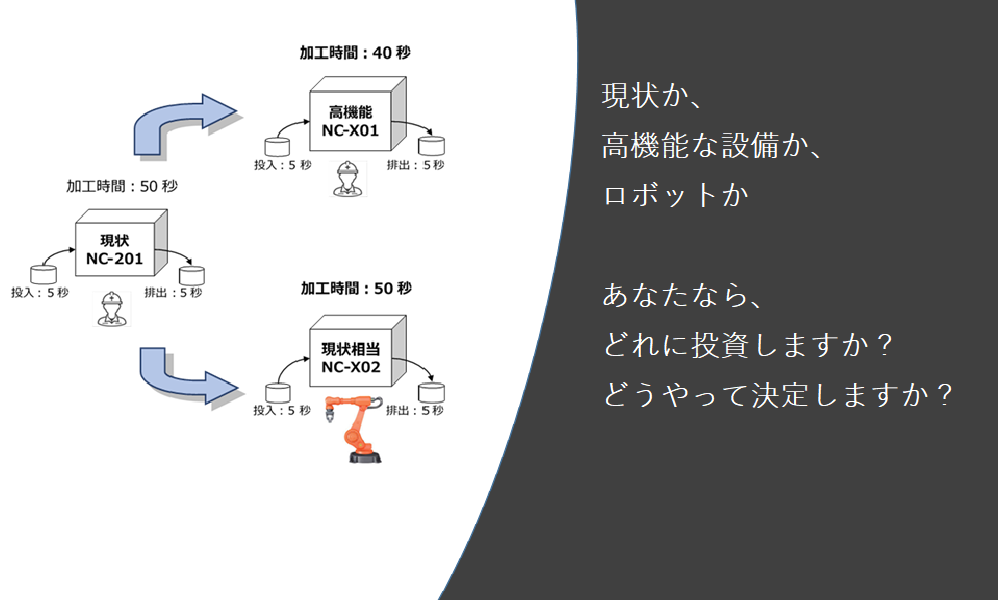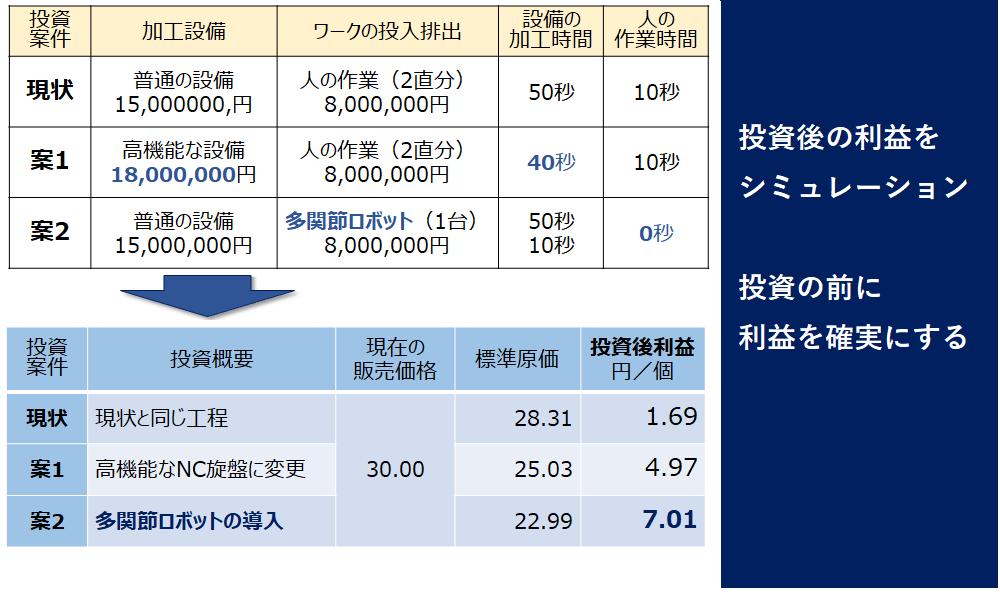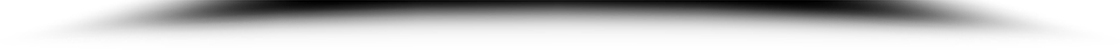「儲かる原価計算」とは
●「儲ける」ためだけを考えた、原価計算の方法です。
●「儲ける」に必要無い手順を排除した原価計算です。
●簡単に、早く、原価を計算し、改善などのアクションにつなげるために考案しました。
●多くの中小企業で実際に活用し、成果を上げています。
●原価計算は会社、組織に絶対、必要です。
(参考 原価計算の必要性)
「儲かる原価計算」の分類
|
このページの内容 |
「儲かる原価計算」の必要性
本サイトの管理会計、原価計算は、「原価計算基準」など、法人税法や企業会計審議会が求める「一般的な」「財務会計の」ための原価計算ではありません。
「一般的な」「財務会計の」というと、「基準」や「規則」となり、その会社、組織に必要のないもの(理論や理屈)まで、無理に適用させようとします。
ここでいう「必要のない」とは、「儲ける」に直結しないものです。
たとえば、企業会計基準に「棚卸資産(在庫)の評価」がありますが、この評価に、原価計算が必要になります。
これは、損益計算書の利益を算出するにあたり、統一的なやり方、基準が必要ということで設けられています。
この「棚卸資産(在庫)の評価」のための「原価計算」に、とても手間が掛かります。
損益計算書の利益から、具体的な行動、アクションは生まれません。
 「損益計算書」は今すぐ捨てろ
「損益計算書」は今すぐ捨てろ
と言うか、究極は、在庫は無い(ゼロ)状態が理想なのに、そこに時間と労力を掛けるほど、企業に余裕はありません。
これが、原価計算を難しく、苦労して導入した原価の管理、運用を大変にしている要因です。
すると、どうなるか
- 難しいから、理解できない
- 難しいから、片手間ではできず、導入まで至らない
- 導入しても、管理、運用ができず、その内、使用しなくなる
一般的な原価計算の通りにやっていては、いつまで経っても原価計算ができません。
そこで、簡便な方法を使って、早く原価計算を行い、早くアクション、行動をお越すための、「儲かる」に繋げるための「原価計算」を考えました。
それが、
「儲かる原価計算」のベース
但し、「一般的な」管理会計、原価計算は「原理原則」として捉え、ベースにしています。
なぜなら、計算の過程、方法は、だれが考えても同じようなやり方になります。
それは、現地現物で費用、原価の発生を追っていくと、自然にその計算方法になるからです。
よって、「一般的な」と同じような考え方、計算方法になります。
本サイトの「儲かる原価計算」でも
- 原価計算のやり方を目的に応じて、分けています。
(見積原価・実際原価・標準原価) - 原価計算の計算過程も「工程別」から「製品別」という計算順序で算出します。
なので、「工程別総合原価計算」や「個別原価計算」をベースにしています。
「儲かる原価計算」のポイント
「実際原価計算」において、工程間にある仕掛在庫は考えないものとして、いわゆる「ころがし」計算は行いません。
そのため、仕掛在庫の入出庫も発生しないものとして、「移動平均」や「先入れ先出し」「総平均」の計算も行いません。
「儲ける」に必要ないからです。
原価計算を難しく、且つ、管理、運用を大変にしている「ころがし」計算を排除することにより、原価計算の導入を簡単にしています。
この「ころがし」計算がなくても、実際の実務では十分、使用、活用できる「儲かる原価計算」を考えました。
次のページ、「儲かる原価計算」の概要もご覧ください。